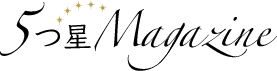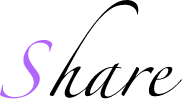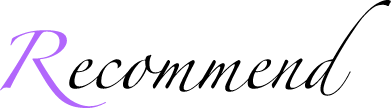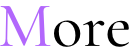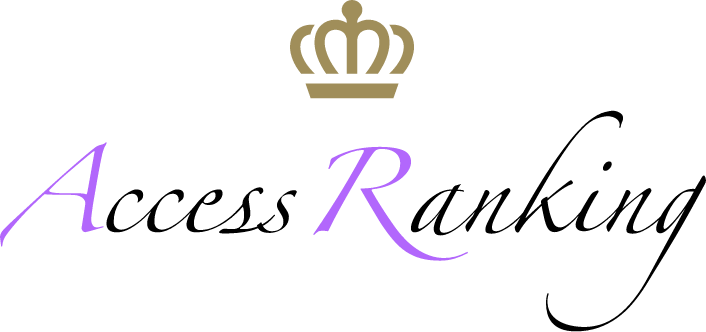世界のセレブが愛する、日本のクラフト・キャビア「1983 JCAVIAR」

世界三大珍味の一つとして知られるキャビア。黒く輝くそれは「海の宝石」とも呼ばれ、世界中のグルメから愛されています。キャビアはロシア産が有名ですが、国内でも生産されており、中でも先駆者と言えるのが宮崎県の通称「宮崎キャビア1983」です。和食にも合う豊かな味わいで、4年連続ANA国際線ファーストクラスの機内食に選ばれ、日露首脳会談やG7伊勢志摩サミットの料理にも採用。国内外の有名シェフが絶賛する1983 JCAVIARジャパンキャビアをご紹介しましょう。
初の国産キャビアの誕生
キャビアとは

キャビアとは、チョウザメの卵を塩漬けにしたものです。チョウザメは、姿形がサメに似ているためにそう呼ばれていますが、サメとは系統が異なる淡水魚。つまり川で生まれて海で育つ魚です。天然のチョウザメは、キャビアをとるために乱獲されて激減したため、捕獲が禁止され、1990年以降は養殖が盛んに行われています。
宮崎キャビア1983の始まり
1983年に友好の証として、ロシアから日本政府へ寄贈された200匹のベステル(チョウザメ)が宮崎県水産試験場に導入されました。1988年、ここで育てたチョウザメから初めてキャビアを製造。1991年に、国内で2例目のベステルの人工ふ化に成功します。その後、2004年にシロチョウザメの完全養殖に成功し、民間での養殖が始まりました。
ここから長い時間をかけて国産キャビアの製造販売につなげた、ジャパンキャビア株式会社の坂元基雄社長にお話をうかがいました。
キャビアを手がけるきっかけ

2007年当時、私は建設会社の営業部長兼新分野開発室長として、新事業を探していました。宮崎県がキャビアの養殖に力を入れたいと聞いて、事業計画を作ったのが最初です。でも、養殖場の建設費用に加えて、実際に卵がとれるまで10年もかかるという、長期にわたる投資が必要なビジネスは厳しいと感じていました。ただ、勤めていた会社に使っていない鮎の養殖池があったので、試しに100匹だけ育てることになったんです。
他にも養殖を始めた事業者はあって、その多くはリタイア後に「新しい夢を追いかける」という70代以上の人でした。「10年後、国産キャビアを世界に」と皆が語る夢を聞くうちに、私もワクワクしてきてのめりこみました。そして2011年に、年間5万匹という安定した生産体制ができました。
県内に養殖業者は11社あり、それぞれが加工場を作ると設備投資も大変だし、狭いエリアに11のブランドができてしまう。それより一つのブランドを作ったほうが力を集中できる、と提案しました。そして準備を進めて2013年に、宮崎キャビア事業協同組合を設立。その時に、他の人は養殖に専念したい、ということで私が事務局長を引き受けることになったのです。安定した会社員を辞めることに迷いはありましたが、新しい事業への夢や、日本初のキャビアとして先行者利益もある、日本一になれるのではないかと決断しました。養殖を手伝いながら海外の情報を集めて、キャビアに可能性を見出してもいました。
キャビアの製造に苦戦
キャビアは熟成が必要だった・・・

様々なキャビアを海外から取り寄せ、おいしいものを見つけては参考にしました。キャビアはできたのですが、フランス人シェフに私たちのキャビアを食べてもらうと、「これはキャビアじゃない、おいしくない。このキャビアは熟成させているのか」と酷評されたのです。私たちは熟成させることを知らなかったんです。海外のメーカーに聞いたら、皆熟成させていると言う、でも、企業秘密だから誰も教えてくれない。自分でやるしかありませんでした。幸いというか、私は工学部出身なので、実験してデータをとって、改良していく作業の繰り返しは平気。熟成させるために最適な温度や湿度などの環境、塩加減、熟成期間などのデータをとり、試験を繰り返していきました。
そして行き着いた製造方法

輸入キャビアの多くは、保存のために防腐剤を使い、低温殺菌、5~8%の高塩分処理が行われています。私たちのキャビアは、素材の旨みを損ないたくないので防腐剤を使っていません。そのため低温状態で手作業で不純物を丁寧に取り除き、自社ブレンドの岩塩で薄く味付けをして、専用の容器に入れて数カ月熟成期間を置きます。アミノ酸が増えて、最もおいしい状態になったタイミングで急速冷凍して味の変化を防ぐのです。
和食に合うキャビアが評価される


伊勢志摩サミットの料理に採用

発売初年度、製造できたのはわずか600個ですぐに完売となりました。その後、2014年に純米大吟醸の日本酒で知られる「獺祭」とのコラボが決まりました。当時、東京・京橋にあった獺祭の直営店で、宮崎キャビア1983と獺祭のセットメニューを限定100セット用意すると、すぐに完売しました。第2弾の「MIYAZAKI CAVIAR 1983 Premium×獺祭 磨きその先へ」の数量限定プレミアムセット(54,000円)は80個のみの販売。獺祭のブランド力と豊かな客層に受け入れられたという手応えを感じました。


※料理はイメージです。実際のサミットの料理とは異なります
そして2016年には、G7伊勢志摩サミットの料理に採用されました。食材のほとんどが三重県産材料という中で、宮崎キャビア1983と北海道バターなど、何種類かだけが県外産でした。
日本料理に合うオリジナル「和キャビア」


「日本人が美味しいと思えるキャビアを作ろう」というのが宮崎キャビア1983のコンセプトです。日本にはカズノコやイクラ、明太子、カラスミなどの魚卵を食べる文化があります。これらは塩だけじゃなく、ダシや醤油を加えておいしく作られています。いつかそういうもの、つまり和食に合うキャビアを作りたかったんです。
祇園 さゝ木とのコラボ

そんな中で京都の名店、祇園 さゝ木の佐々木浩さんと会う機会があり、昆布の風味のキャビアがほしいと言われて、しめた、と(笑)。2年ほどかけて一緒に作りました。難しかったのが、昆布は浜辺で天日干しするため、自然にあるいろんな雑菌がつきます。それが旨みにつながり、料理に使う時は熱を加えて殺菌できます。ところが、昆布に熱を加えると粘りが出て糸を引いてしまうし、熱を加えないと熟成途中で傷んでしまいます。
佐々木さんから、糸をひくキャビアも日本人は受け入れる、と言われてなるほどと思ったものの、納豆ほど強い糸ひきはキャビアらしくありません。昆布の加熱温度を、ダシが出てキャビアが痛まないギリギリのタイミングに合わせ、粘りもほどよい加減にしました。祇園 さゝ木のお客さんにも大好評で、和食に合うということが証明されました。

祇園さゝ木「CAVIAR JAPAN」20g 14,040円(税込)
京都吉兆とのコラボ
京都吉兆の徳岡邦夫さんからは、醤油を加えたキャビアが欲しいと言われました。すでに昆布が使えるのはわかっていたので、醤油をどう入れるかを研究しました。キャビアは専用の熟成容器に入れて何カ月か寝かせるのですが、醤油やダシを加えると皮が薄いキャビアはベチャベチャになるんです。熟成させながらダシと醤油の旨味をキャビアに入れて、水分は抜く、という新たな熟成容器を開発しました。自分で図面をひいて設計したオリジナルですので、他社は真似できないと思います。

京都𠮷兆 嵐山本店「熟成うま味キャビア」12g 16,200円(税込)
日本のキャビアに合うお酒は…

宮崎キャビア1983 プレミアム(12g) 8,640円(税込)
1983年、「日本が世界に誇れるようなキャビアを作る」という目標を立てて始まりました。それから30年という長い年月を経て2013年に、純国産熟成フレッシュキャビア「宮崎キャビア1983」が完成しました。徐々にお客様が増え、昨年、星野リゾートが日本中のキャビアをブラインドでテイスティングして、私どものキャビアを選んでいただきました。

宮崎キャビア1983(12g)とJCAVIARウォッカ750mlセット 10,800円(1983 JCAVIAR VODKAのみの場合は5,500円)
キャビアといえばシャンパン、というイメージがありますが、私が一番合うと思うのは、旨みのあるすっきり系の日本酒です。日本酒とキャビア、両方の旨みのバランスがとれたとき、得も言われぬ味わいになります。キャビアの本場ロシアではウォッカと合わせます。そこでキャビアに合うウォッカ「JCAVIARウォッカ」を造ってみたところ、これも好評です。
ウイスキーならスコッチ系もいいですね。海辺で造られているものは、樽に潮の香りや成分が含まれているから魚卵であるキャビアとよく合います。
テレビのトーク番組で、ゲストの実力派俳優がイチローズモルトを持参した際に、おつまみとして宮崎キャビア1983を紹介してくれました。びっくりしましたが、司会者である国民的アイドルの方の口に合ったようでうれしい限りです。他にも、国産のシングルモルト系は宮崎キャビア1983とよく合います。
2013年11月にMIYAZAKI CAVIAR 1983を発売してから、何もないところに道を作る日々でした。大変でしたが一つ一つ壁を乗り越えていく達成感があります。宮崎の山奥の美しい自然の中、人の生活が無い、上流の清らかな水で育てているチョウザメ。そのキャビアの濃厚な旨みをぜひ味わってください。

1983 JCAVIAR バエリ クラシック(12g) 7,020円(税込)
◎宮崎キャビア1983が食べられる店
パークハイアット東京
シャングリ・ラ東京
ザ・リッツ・カールトン京都
セントレジスホテル大阪
京都𠮷兆 嵐山本店
祇園さゝ木
星のや 富士
界 加賀・出雲 ほか多数
取材を終えて
宮崎キャビア1983を食べた時、料理の添え物ではなく、キャビア自体を味わうメニューでした。丸いケースに入ったキャビアを小さなスプーンですくって口に入れると、豊かな味わい、そのあふれる旨味に驚かされました。塩味だけのもの、だしと醤油が入ったもの、どちらもわざわざ取り寄せる価値ありの逸品です。
ジャパンキャビア株式会社
宮崎県宮崎市瓜生野6388-7
TEL:0120-886-863
https://www.japancaviar.jp/
https://store.japancaviar.jp/