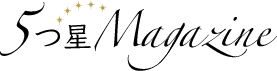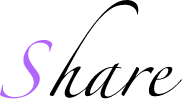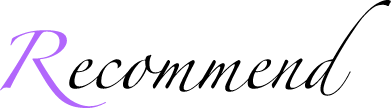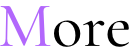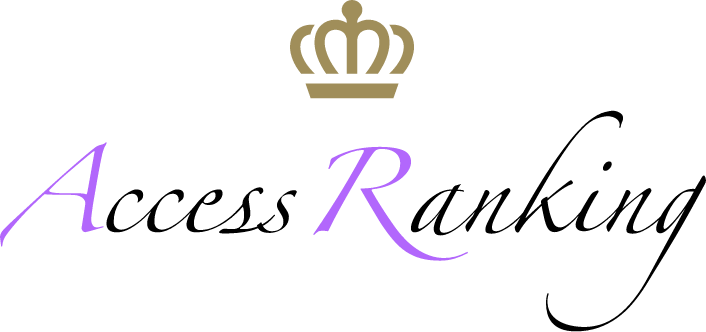吉岡更紗さん 染司よしおか6代目。よみがえる伝統文化「植物染」。季節に色をかさねて

茜、萌黄、紅梅…、古来日本では色を表す言葉に季節を重ねてきました。このゆかしい文化を今に伝える染色工房が京都にあります。花や実、草木の根など、天然の植物から抽出した染料で手染めする老舗「染司よしおか」です。
四季を表現するかさねの色
暦を色で彩る

現在使用されている太陽暦の前、暦は長きにわたって太陰太陽暦(二十四節気七十二候) が使われていました。「立春」や「立冬」など、1年を24等分した二十四の節、さらにそれぞれを3等分した七十二候です。暦では4~5日毎に季節が移り変わるとされ、これを色で表現する文化が生まれました。色は暦に合わせて気候や行事、植物の名前などで表されたのです。
かさねた色で殿方にアピールする姫君たち
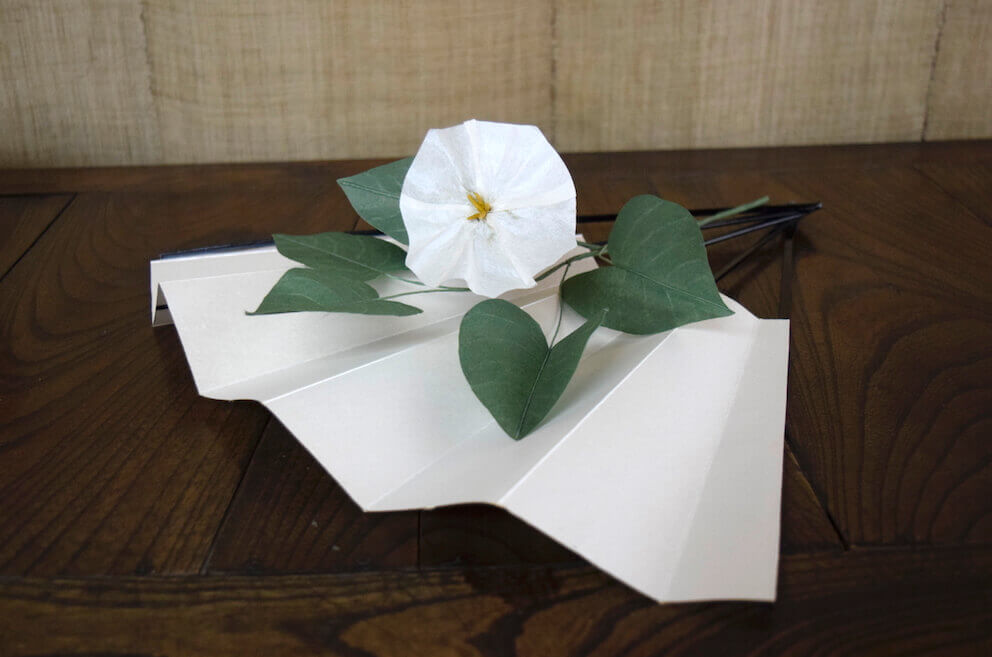

ロンドンのジャパン・ハウスギャラリーに展示された「源氏物語」をイメージした作品
1200 年以上前、平安時代は、十二単に代表されるように、柄ではなくかさねた衣装の色の組み合わせで個性を出していました。四季の細かい移り変わりを衣装に映すことが上流階級の人々にとってのおしゃれであり、富と教養の表れだったのです。
当時の貴族は、未婚の女性が男性と顔を合わせることはなく、御簾越しに衣装の裾(出衣:いだしぎぬ)のかさねの色で外の男性に自分をアピールし、歌を詠みあうことから恋愛が始まりました。自分をアピールする手段が色の組み合わせだったのです。夏は夏の色で、冬は冬の色で表現する。このような「かさね」の着こなしについて、源氏物語にもしばしば表現されています。
古の植物染の色を復活

吉岡更紗さん
かさねの一番上を薄物といい、白い無地のものや、下の色を拾って綺麗に見えるように透け感の出る織り方のものが用いられていました。透ける布には様々な種類があり、日の光や透過した色の重なりで何種類もの違う色を表現していました。「当時の人は色に対して細やかな感覚を持っていたと思います」と染司よしおかの6代目となる吉岡更紗さん。
数日ごとに変わる日本の季節の色を表現するためには、繊細な色の表現やそのための技術が必要です。その染色方法こそが、よしおかが復活させた植物染だったのです。

染司 よしおかの歴史と技法
時代は化学染料へ

よしおかの歴史を振り返ってみましょう。創業は江戸時代、初代は今のように自然の植物のみで染めていましたが、明治時代になって鎖国が解かれ、化学染料が海外から入ってくると、新しいもの好きの京都の文化が後押しし、京都の染物屋はほぼ化学染料に取って変わりました。よしおかも、この時代の2代目から3代目までは化学染料のみを使っていました。
植物染に魅せられて

転機は4代目が京都の町なかから伏見区に移転したときでした。たまたま古い染物を目にし、昔の染物のほうが色が美しいと感じた4代目は、すぐに植物染の研究を始めます。
ちょうど戦後の景気回復の時期で、呉服産業が急成長した頃。商売も繁盛しており、その売り上げを研究費にあてて研究に没頭したのです。植物染はすぐに市場に受け入れられ、呉服屋とのタイアップもあって、よしおかの染物は徐々に天然染料の割合が増えていきました。
植物染料を中心に研究していた4代目ですが、ヨーロッパで貝から紫の染料を抽出する方法があることを知ると、ナポリに行って、その方法を調査・研究してきました。そして、 昔はローマ皇帝しか着てはいけないとされていた色を染めた着物や帯を商品化したのです。
天然染料のみで染める

そして、5代目が更紗さんの父、染織史家の吉岡幸雄さん。美術図書の編集者、アートディレクターとして活躍していた40代半ばに、4代目である父の死によって急きょ家業を継ぐことになります。このとき化学染料を完全にやめ、天然染料だけで染める決意をします。それは、編集者として日本のみならず世界中の染織品を見てきた経験から、植物が生み出す色の美しさに魅せられていたから。今、天然染料を扱う作家は多いけれど、工房として商売にしているのは、藍染を扱っているところ以外ではほとんどありません。
過去の文献にある素材のみを使う

よしおかが一般的に植物染と言われている染物屋と大きく違うところは、化学染料が入ってくる前の時代に使われていた、昔の文献に記録のある染料しか使わない点です。 定着液の原料も同様。銅や六価クロムなどを使用して植物染をする工房もありますが、それも結果的には自然を汚してしまうことになる。長い年月をかけて先人が残してくれた天然染料の記録には、失敗を繰り返しながら良い染料で美しい色を作り出す例がたくさん残されています。それを復元するのが、よしおかの仕事。たとえ山を散策したときに、染料となる植物を見つけたとしても、それが記録になければ使うことはしない。それが“よしおかのこだわり”なのです。
自然の色にこだわり、季節とともに仕事をする

染色に限らず、珍しいものに注目し、新しいものを取り入れるのが京都人気質。しかし、よしおかは逆に昔に返る仕事にシフトし、それが国内外の人々に受け入れられました。
技法に関してはオープンにしていますが、作業時間もかかり、材料費も安くないため、なかなか追随する工房はありません。自然染料のみで染物屋としてやっていくのはとても大変なことなのです。
使う材料が自然のものなので、当然、植物の成長サイクルに合わせた仕事の仕方になります。仮に化学染料から切り替えたとして、仕事のサイクルを植物に合わせようとすると、立ち上げに数年かかり、それを継続していくのはさらに難しいのです。 たとえば藍染だと、かめの中で染料を発酵させるので、寒い冬より暑い時期のほうが発酵が進むため、夏が一番美しく染まります。このように、植物に合わせて仕事の時期が決まるため、効率優先の現代ビジネスにはなじみません。
しかし、敢えてよしおかは植物染にこだわります。 紅花の花の時期は夏ですが、「寒の紅花染」と言われるように、夏に花を摘み、花を乾燥させてから冬に染めるのです。これが、綺麗な濃いピンク色に染める手法です。紅花の黄色の色素は水に流れてしまうので、残った赤い部分のみが染料となります。その赤を取り出すには、米を収穫した後の稲わらを燃やした灰を湯に溶かし、そのアルカリ水で紅花を揉みます。その稲わらがとれるのも秋以降になるので、冬にならないと染料作りができません。このように、美しい自然の色にこだわるがゆえの、植物カレンダーに合わせた仕事が、よしおかの染め方なのです。
日本に伝わる色の名前

染色は昔の方法でも、色の組み合わせで現代のモダンを表現することができます。一見きつい赤と緑でも、着物の組み合わせだと、とてもモダンになり、むしろ新鮮に感じられます。高価な着物は何枚も持てませんが、重ね衿で工夫するなど、現代でも「かさね」はおしゃれとして使われています。
日本には 200~300 種類の色とその名前があったと言われています。その種類は、急に何百とできたわけではなく、徐々に増えていきました。 初期は茜色、苅安色など、染料となる植物の名を用いるものが多く、平安時代になると季節の移り変わりを衣装で表すため、色の数も増えていきました。江戸時代になると身分によって着るものの色が制限され、贅沢禁止令によって町民は茶色やグレー、黒しか着られなくなります。それでもいろいろな茶色やグレーを作り出し、四十八茶百鼠と言われるように、新しい色と名前が増えていきました。自由がないなかでも、人々は着るもので粋やおしゃれを楽しんでいたのですね。
天然素材の布に染める

平安時代、華やかな着物を着ていたのは都に住む一部の貴族のみだったため、かさねの色にこだわる文化は、限られたものでした。 染料が一番よく染まるのは絹ですが、庶民は麻、藤布(ふじふ)、葛布(くずふ)などの植物のツルを割いて繊維をとり、その繊維を織っていました。自然布、原始布と呼ばれるものです。しかし、それらは染物としてはうまく染まらないため、生成りや藍染、茶系の色のものを着ていたと推測できます。
木綿は中国やインド(天竺木綿)から入ってきましたが、日本で綿が育てられるようになったのは、江戸中期以降です。原産地はインドやエジプトなど気温の高い地域なので、日本の寒い気候でも育つように品種改良されました。ちなみに観賞用の植物の品種改良が始まったのも同時期だと言われています。
木綿の栽培ができるようになって、庶民の着物に木綿が広がりました。絹はどんな染料でも染まりますが、木綿や麻は藍染と相性がよいため、藍の産地周辺には紺屋という藍染専門の染物屋ができました。江戸時代の終わり頃には、それまでの生成りにとって代わって、藍染を着る人が一気に増えます。明治時代になって、海外から来た外国人が日本人は藍染ばかり着ていると文献にも残しており、その印象から「ジャパンブルー」という言葉が生まれました。
かさね衣装の文化

飛鳥から奈良時代にかけての日本は、中国大陸からの影響を大きく受けていましたが、 遣唐使の廃止によって、日本独自の文化へと進化し始めます。それが平安時代中期に貴族の衣装に象徴され、のちに着物となった直線裁ちの「かさね衣装」です。 かさね衣装は、直線裁ちゆえに何枚も絹布を重ねて着ることが容易であり、仕立てのサイズを少しずつ変えることで、襟元、袖口、裾などに「かさね」を作りました。
江戸時代、武士の間で有職故実が重んじられるようになると、平安時代の文化が見直され、かさね色の組み合わせを研究することが流行りました。それが文献として残されているのです。 「平安時代の装束は応仁の乱で焼失し、残存するものがほとんどないので、この江戸時代の研究書物をもとに色を復元しています」と吉岡更紗さん。
引き継がれる年中行事とよしおかの植物染

よしおかには、年中行事とも言える大きな仕事が2つあります。ひとつは、東大寺のお水取り「修二会(しゅにえ)」の際に二月堂の十一面観音の周りに飾られる椿の花に使う和紙の制作です。紅花で染めた赤い和紙とくちなしで染めた黄色の和紙を、毎年2月23日までに東大寺に納めます。赤と黄、それぞれ60枚くらいの和紙を納めるために、染めの作業は約 2ヵ月かかります。そのため、1月、2月は、ほぼこの作業に追われます。毎年、選ばれた練行衆が、この和紙で約500個の椿の花を作り、本物の椿の木に花を挿して、春を告げる盛大な行事、東大寺のお水取りが行われます。

また、薬師寺の春を告げる行事「花会式(はなえしき)」にも、薬師三尊に飾られる十種類の花の内4種の花に使われる和紙を納めています。薬師寺は7月までには納めることになっており、春から夏にかけてはこの作業に追われます。どちらも春を迎える仏事であり、責任ある仕事です。
源氏物語や枕草子には、「季(とき)にあいたる…」という、季節に合わせた衣装や文の和紙の色使いを褒める言葉が多く使われています。日本の伝統的な「色の文化」は、21世紀の今、ふたたび多くの人から注目され、吉岡幸雄さんは海外での個展が高く評価され、更紗さんも国内外で講演をするなど親子で活躍中。古き時代の色をよみがえらせるよしおかの植物染は、時代を超えて「かさねの色」として世界に羽ばたいています。


染司よしおか(そめのつかさよしおか)京都店
住所 京都市東山区西之町 206-1
TEL&FAX 075-525-2580
公式HP
https://www.textiles-yoshioka.com
https://www.sachio-yoshioka.com